質問への返答1
すっかり春らしくなってきましたね♪
雪もこの数日でずいぶん溶けてきた飛騨地方です。
さて、
先日おこなった講演会(2014年11月27日木 高山市民文化会館にて 医療法人三紲会とスマイルネットの共催で嚥下の講演会)
の際にお預かりした質問について
国民健康保険飛騨市民病院 理学療法士 井出浩希先生よりお返事をいただきましたのでブログで紹介させていただきます。(ブログへの掲載は、井出先生の許可をいただいております)
質問:ゼリーがなぜいけないのか?
まず誤嚥と窒息の違いについて理解しておく必要があります。
誤嚥:誤って食物が声門(気管の入り口)より先に入ってしまうこと。
窒息:空気の通り道を食物などが塞いでしまうこと。窒息は気管の中に入らなくても起こります。
気管の入り口に食べ物が乗っかった場合、口の中に大量に物を詰め込んだ場合、口を手で塞がれた場合があります。
そして嚥下障害の患者さんの食事の形態を考えるとき
「付着性」「流動性」「凝集性」を基本に考えます。
1.付着性(粘膜へのくっつきやすさ、口やノドを移動する速度の速さ)
残留しても粘膜に張り付くので誤嚥しにくい。
大きな塊で残留すると粘膜に張り付き気道を塞ぐので窒息しやすい。
餅が窒息しやすい原因は、付着性が非常に高く、まとまりもよすぎるので、ノドで大きな塊になりやすく、大きな塊のままノドに張り付きやすい物性があるからです。
舌や口の中にも張り付くので、送り込みがしにくくなる。
張り付きやすいので、口やノドを移動する速度は遅くなる。
2.流動性(形の変わりやすさ)
形が変わりやすい(流動性が高い)と気管を塞ぐ力が少しでも遅れる、不十分な場合に入り込んできやすい。
つまり誤嚥しやすい。
食道の入り口が開きにくい場合には、形が変わりやすい(流動性が高い)方が通りやすい。
ノドや口の中で形が変わりにくい(流動性が低い)と空気の通り道を塞ぎやすく窒息しやすい。トロミが濃い
3.凝集性(まとまりやすさ)
まとまりが悪いと、ノドでばらけてしまい誤嚥しやすい。
どんな食物でもこの3つを中心に考えて、患者さんの嚥下機能(咽頭期(ムセ、残留)、口腔期)と組み合わせて考えれば問題ありません。でもそれが難しいというのが事実です。
【嚥下障害患者さんによいと言われているゼラチンゼリーの基本的な物性(性質)として】
・体温で溶けて離水する(水と固形物に分かれ二相性になる)
・流動性が高い(中には固いものもありますが)
・付着性が低い(ノドや口を移動しやすい、動く速度が速い)
・クラッシュすると凝集性が低い(ばらばらになりやすい)
・商品によっては舌で潰せるくらいに柔らかい。という点があります。
*嚥下障害患者さんにゼリーを食べて頂く際の注意点として、嚥下障害治療の第一人者である浜松リハビリテーション病院の医師藤島一郎先生は、5mm幅のスライスカットとし、丸呑みが基本であると仰っています。
これはどういうことかというと、
口腔期(頬や舌、咀嚼)に問題があり、飲み込むときに食べ物がバラバラになってしまう患者さんや送り込みができない患者さんを対象としているということです。
適応は口腔期障害が中心と考えています。
次につづきます
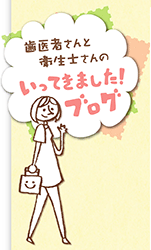

コメントを投稿するにはログインが必要です。